 |
|
|||
| DATA |  |
|
| ■設計:安藤忠雄建築研究所+森ビル ■所在地:東京都渋谷区神宮前4-12-10 ■用途:店舗、共同住宅(38戸) ■竣工:2006年(平成18年)1月 ■規模:敷地面積6051.36m2、建築面積5030.76m2、延床面積34061.72m2 ■構造:SRC造、一部RC造・S造 地上6階地下6階(最高高さ23.3m、最高深さ31.4m) ■開発手法:第一種市街地再開発事業(組合施行) ■付近の地図(mapion) |
||
zoomマークが付いた写真はクリックすると拡大表示します。 (※JavaScriptを使用しています) |
外観について。
誰が見てもすぐ分かる特徴は、ケヤキ並木を越えないよう配慮された「高さ」と、とてつもなく長い「間口」です。ただ低層へのこだわりは良いとして、これだけの長い間口を活かせていないのは大いに気になります。
コレッツィオーネやTIME'Sもそうだけど、やはり安藤忠雄は造形を魅せる建築家であって、人間同士のコミュニケーションの場を提供するのは苦手、要するに美術館は上手いが商業は全然ダメな気がします。双子の弟である北山孝雄が関西テイスト全開でコミュニケーションの場をプロデュースしているのとは(やりすぎると収拾がつかなくなりますが)あまりに対照的ですね。
次に内部について。本館には「スパイラルスロープ」と呼ばれるスロープが設けられていて、内部の店舗を一筆書きで巡ることができます。スロープの傾斜は表参道と同じ5%、スロープの延長も表参道と同じ700mとなっており、「建物内に第2の表参道」という明快な表現がされています。(写真#6,#10)
さて、店舗にとって何が重要かというと、視認性と人通りです。店の存在をアピールできれば客が来てくれますし、目の前を多くの人が歩いていれば偶然立ち寄ってくれる確率が高まります。通常の百貨店などでは売り場がフロア毎に分かれているため、階によって人出が全く異なることが多いわけですが、このように一筆書きとすれば地下深くまでどのフロアにもまんべんなく人を引き込むことができます。しかも吹き抜けが適度に小さいので、スロープから”対岸”を見るとどんな店があるのか良く分かる(=視認性が高い)。今後時間を経てテナントが入れ替わったとしても極端に賃料の安い店舗区画は発生しにくく、ビル経営上は有利です。
吹き抜けは従前の青山アパートの棟間空地に沿わせて設計されています。いかにも建築家らしい解の求め方ですが、遠近法効果もある絶妙の形状になっています。(写真#6,#7) また、天井にはライト、プロジェクター、指向性スピーカーなどが設置されていて、地下深くの大階段に映像を投影することもできます。(写真#8)
神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業
Omotesando Hills
かつてこの地に建っていた同潤会青山アパートは、(関東大震災からの)震災復興及び建築不燃化という文脈の中で1927年に建てられた、日本初のRC造集合住宅(マンション)といって差し支えない、歴史的価値の高い重要な建物でした。ただし間取り等は現代のニーズに適合せず、1960年代には早くも建て替えの話が出ています。その後バブル期の再開発計画が頓挫し、今回森ビルが強力なリーダーシップを発揮する形で再開発が実施されました。

#1:表参道に沿って長いファサードが続く。間口は220メートル。夜間は外壁面に組み込まれたLEDが光る。中間層免震が採用されており、上層の住宅と下層の商業は構造的に分離されている。
 #2:東端部 |
 #3:手前は同潤館と公衆トイレ |
 #4:ヒルズ効果で通行人は増えたが、立ち止まることはない。 |
 #5:メインエントランス付近 |
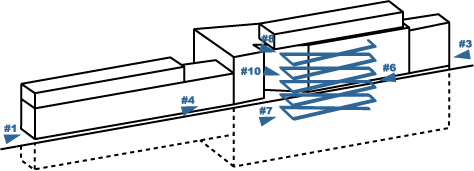 |
|||
 #6 |
 #7 |
 #8:眼下の大階段に映像を投影できる |
 #9:大きめの情報パネル |
 #10:スパイラルスロープの幅は大人四人分くらい。スロープの傾斜(5%)は表参道のそれに合わせてあり、思ったほど苦痛ではない。”対岸”にある店舗の視認性は高い。全館避難安全検証法(補注1)の認定を取っているので、防火シャッターのないスッキリした空間となった。 |
|||
 #11:スロープと平板の微妙な段差を処理できていない。写真の左上には警備員の姿が。 |
 #12 |
||
 #13 |
 #14:同潤館からの並木。 |
 #15 |
 #16 |
 #17:同潤館への連絡通路。どうもおさまりが悪い。 |
 #18:裏側はこんな感じ。 |
||
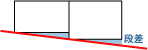
安藤はこの問題をどう解くのかな?と期待していたのですが全然解決しておらず、結局足元に注意して歩く以外にありません。特に大階段の踊り場とスロープの境界線は危険なようで、黄色と黒で強引にマーキングした上に警備員を配置しています。(写真#11) これはバリアフリー云々以前に健常者にも危険な仕様で、かなりガッカリします。
有名建築家だからバリアのある建築でも実現できた(批判を押しのけられた)と賞賛する人もいるでしょうし、建築家の本能的エゴと非難する人もいるでしょうが、私は不特定多数が出入りする建築としてはやはり問題だと思います。大型回転ドアほどのリスクじゃありませんが…。
あと、本館から同潤館への連絡通路(写真#17)について。おそらく青山アパートの復元にこだわったために動線の取り回しが上手くいかなかったのだろうと想像しますが、”新旧の共存”を訴えるなら新旧の接合部は重要なポイントになるわけで、もう一工夫欲しいなぁと感じました。

#19:同潤会青山アパートのレプリカ「同潤館」。オリジナルの竣工当初はこういう色だったという(手すり等は一部再利用している)。世界のANDOの力をもってしても、こういう”直喩”は難しい。接合部の処理の仕方も最適解には見えない。
ANDO建築がどうのこうのばかりを見ていると、この建物の重要な本質を見逃してしまいます。再開発ビルとしての表参道ヒルズについては、後日執筆・更新します。
[補注]
(1) 根拠は建築基準法施行令129条の2の2。火災発生時に中にいる人が逃げるまでの間、煙やガスが充満しないことが確認できれば、防火シャッター設置などの規制を緩和することができる。
[参考文献・サイト]
1) 表参道ヒルズ公式サイト
2) 建築マップ 青山アパートメントハウス
3) 「日経アーキテクチュア」2006年4月10日号pp8
4) 「再開発コーディネーター」120号pp8-11

#20:取り壊し前の青山アパート。時を経て育った「地霊」の魅力は代え難いものがあった。
 |
作成:2006/4/15 最終更新:2006/4/28 作成者:makoto/arch-hiroshima 使用カメラ:Nikon D70 |
| 文章の引用、写真の使用に関してはこのサイトについてを参照の上、個別にご相談ください。 If you wanna use text or photo within this page, please contact me. |